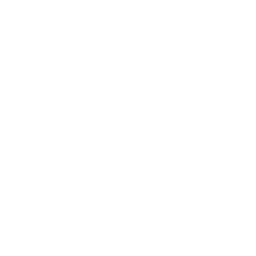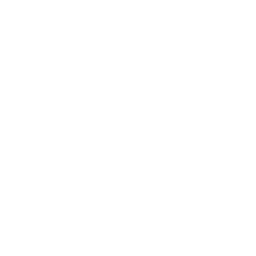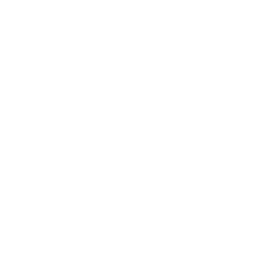アロハシャツのルーツと歴史 ─ 日本・沖縄・ハワイをつないだ一枚のシャツ
はじめに
アロハシャツは今やハワイの象徴とも言えるファッション。けれど、その“存在感”の正体を辿ると、ハワイだけでは説明がつかない、実は奥深いストーリーがあります。
この記事では、アロハシャツがどんな時代背景の中で生まれ、どんなルーツをたどって「今の一枚」になったのかを整理します。1930年代のハワイを起点に、武蔵屋(ムサシヤ商店)や着物生地、商標登録、そしてサトウキビ畑の暮らしまで、1つずつ繋いでいきます。きっと読み終えたころには、アロハシャツの見え方が少し変わってくるはずです。

アロハシャツのルーツは、ひとつの場所だけでは語れない
アロハシャツはハワイの服です。けれど、ハワイの景色だけで語るにはもったいない服でもあります。あの一枚には、暮らしの中で育った“芯”がちゃんとあります。
ハワイの光と風の中に、日本の布が入り、移民の暮らしが入り、やがて「Aloha Shirt」という言葉が印刷され、商標登録で“名前のある商品”になっていく。アロハシャツは、そうやって複数の土地と暮らしが重なってできた服です。
そしてこのストーリーは、日本本土だけでなく沖縄にもつながっています。沖縄からハワイへ渡った人たちは多く、島々には今も「ハワイ」という言葉が、どこか生活の手触りとして残っています。宮古島でも、おじいたちが「みんなハワイに行きたがっていたよ」と話すように、海の向こうのハワイは遠いのに近い存在でした。
その距離感のまま、アロハシャツもまた“海を越えた暮らし”の上で育っていった服なんだと思います。
1930年代、ホノルルで「アロハシャツ」が名乗りはじめた
アロハシャツの歴史が1930年代から語られることが多いのは、この時代に「服」だけでなく「言葉」と「売られ方」が揃ったからです。
1935年6月、ホノルルの仕立て屋「Musa-Shiya Shoten(武蔵屋/ムサシヤ)」の新聞広告に “Aloha Shirt” が登場した、と紹介されています。ここで初めて、シャツが“呼び名”を持って社会に出ていきます。
その後、この呼び名は商標登録をきっかけに社会の中で定着していきます(商標の話は後半で触れます)。呼び名が固まると、人は同じ名前で探し、同じ名前で買うようになります。流行が「市場」になっていく瞬間です。
サトウキビ畑とパラカ ─ “働くシャツ”が土台になった
ただ、ここでいきなり広告や商標の話だけをすると、アロハシャツが急に“お土産ビジネス”に見えてしまいます。実際は逆で、土台にあったのはもっと生活の側でした。
当時のプランテーションで働く家族には「布が足りない」「買うお金がない」という現実があり、米袋の布まで使ってシャツやショーツを作った――そんな証言を、ハワイの大学研究者がはっきり語っています。つまり、服はまず“工夫して生きるための道具”でした。その現場には、日本本土の人だけではなく沖縄から渡った人たちもいました。言葉も文化も違う土地で働きながら、家族を養い、生活を回す。その毎日の中で、シャツは“おしゃれ”より先に、暮らしの必需品として根づいていきます。
そんな生活の中で、丈夫なチェックの布として知られるのが パラカ(palaka) です。パラカは作業着としてプランテーションで好まれ、長い時間をかけて「ハワイの働く布」として根づいていきます。
ここがアロハシャツの芯になるところで、最初から“リゾートの服”だったわけではありません。まず「働くシャツ」があって、その上に「柄の世界」が重なっていきました。
パラカの発想 × 着物生地の柄 ─ 子ども服から見える原点
ここで押さえたいのは、アロハシャツが最初から「観光のための服」だったのではなく、暮らしのシャツの上に“柄の布”が重なって育ったという流れです。
パラカ(palaka)は、プランテーションで働く人たちが着ていた、丈夫なチェック柄のワークシャツです。強い日差しや汚れに耐えるために、シャツはまず「体を守る道具」でした。つまり、ここにあるのは“おしゃれ”ではなく、生活の必需品としてのシャツです。
一方で同じ時代のハワイでは、日本由来の生地で仕立てたカジュアルシャツが、ローカルの間で着られていたことも語られています。
ここで登場するエラリー・チャンは、ホノルルでシャツを扱った店に関わり、のちに「Aloha Shirt」という呼び名を商標登録した人物として知られています。彼の回想(1964年のインタビュー)では、当時ローカルの少年たちが日本の生地(たとえばチャリス=軽くて着やすい布)で作られたシャツを着ていたこと、さらに彼自身も1930年代初頭に、仕立て屋に和柄の着物地(=反物などの柄布)でシャツを作らせたことが触れられます。
この2つを並べると、流れがはっきりします。
パラカが支えたのは、働く暮らしに必要な「シャツの形」と「実用の感覚」。そこに着物地の柄が入ってきたことで、シャツは一気に目を引く存在になっていきます。派手さのはじまりは、急に“流行が生まれた”のではなく、日常の上に柄が重なった結果です。
ここで少年たち(子ども)の存在が効いてきます。少年たちが着ていたというのは、それが“特別な服”ではなく、日常着として既に浸透していたサインだからです。だから柄のシャツも暮らしの延長として根付きやすかったのだと思います。
そして、柄の話をもう一段だけ深くするなら、絣(かすり)は外せません。絣は、糸を括って染め分け、織りで柄を出す技法です。日本の模様文化の中で磨かれてきた表現で、私が住む沖縄宮古島の宮古上布も、この絣の考え方とつながる織物として紹介されています。
アロハシャツの柄が強く見えるのは、ハワイの景色だけが理由ではありません。布の側に、模様を布として成立させてきた技術と美意識が積み上がっていたからです。
武蔵屋(ムサシヤ)と1935年の広告─名前が、シャツを社会へ連れ出した
暮らしの中で育ったシャツが、社会に広がっていくときに必要だったのが「名前」です。
1935年、ホノルルの武蔵屋(ムサシヤ商店)の広告に “Aloha Shirt” が載った、という話が語り継がれるのは、この一行がシャツを一気に“商品”にしたからです。
名前が付くと、説明しなくても伝わります。人は「それ」として探せるようになり、同じ言葉で買えるようになります。アロハシャツが“定番”へ進み始めたのは、まさにこの地点です。
商標登録、そして“ハワイの顔”へ ─ エラリー・チャンとデュークの時代
商標登録は、夢の話ではなく現実の話です。
エラリー・チャンが「Aloha Sportswear(1936)」や「Aloha Shirt(1937)」を商標登録したことで、呼び名は守られ、同時に広がり方も加速しました。「Aloha Shirt」という言葉が、社会の中で固定されていったわけです。
そして、アロハシャツを“ハワイの象徴”へ押し上げたのは、象徴が着たことです。
サーフィン界の伝説的人物として知られるデューク・カハナモクの名を冠したアロハコレクションが展開された、と語るブランド側の説明もあり、アロハシャツが「ハワイの顔」と結びついていった流れが見えてきます。
生活のシャツが、名前を得て、広く流通し、スターの背中に乗って、観光とともに世界へ出ていく。アロハシャツはこうして、“ハワイそのもの”として見られるようになっていきました。
アロハシャツは“ただの柄シャツ”で終わらない
ここまで辿ると、アロハシャツの魅力は「派手だから」「南国っぽいから」だけでは説明できなくなります。
あの一枚には、当時の暮らしの厳しさや先人たちの工夫、働く現場の空気、日本の布と仕立ての技術、そしてハワイの街で名前を得て広がっていった流れが、ちゃんと重なっています。
だからアロハシャツは、陽気なのにしっかりキマるのだと思います。
ただ目立つだけじゃなくて、着た人の輪郭まで少しはっきりさせる。そういう“芯”がある。そこに、誇りとか、プライドとか、言葉にしづらい魂みたいなものが宿って見える瞬間があります。
アロハシャツがハワイの象徴として残り続けているのは、流行だからではなく、日常着として育った歴史の上に立っているからです。
一枚のシャツなのに、その向こう側に人の暮らしが見える。そこが、アロハシャツのいちばん格好いいところだと思います。沖縄や宮古島からこのシャツを見ると、ハワイはただの憧れではなく、海を越えて繋がってきた現実でもあります。そのつながりごと着られるのが、アロハシャツなのかもしれません。
引用・参考文献
- Patagonia. “The Aloha Shirt: Spirit of the Islands.” (2017-06-20) https://www.patagonia.com/stories/culture/community/the-aloha-shirt-spirit-of-the-islands/story-31160.html
- Ukulele Magazine. “The Birth of the Aloha Shirt.” (2017-02-27) https://ukulelemagazine.com/stories/news/birth-of-the-aloha-shirt
- University of Hawaiʻi News. “The denim of Hawaiʻi: How palaka weaves together …” (2025-09-28) https://www.hawaii.edu/news/2025/09/28/palaka/
- University of Hawaiʻi at Mānoa, CTAHR(College of Tropical Agriculture and Human Resources). “Your Old Clothes Have a Story to Tell.” (2023-01-30) https://cms.ctahr.hawaii.edu/fcs/SiteAdm/Alumni-News-Articles/ArtMID/51791/ArticleID/2611/Your-Old-Clothes-Have-a-Story-to-Tell
- Box, M. “The History of the Aloha Shirt.” 目白大学リポジトリ(PDF)(2006) https://mejiro.repo.nii.ac.jp/record/56/files/KJ00005094769.pdf
- Kona Historical Society. “Palaka: A story about Hawai’i’s hardworking, proud print.” (2020-07-13) https://konahistorical.org/news-blog/palaka-a-story-about-hawaiis-hardworking-proud-print
- Dale Hope(The Aloha Shirt). “History.” https://www.thealohashirt.com/history
- Wikipedia. “Aloha shirt.” https://en.wikipedia.org/wiki/Aloha_shirt
- Son of a Stag. “Culture Clash, Hash Print, and ‘Operation Liberation’ …” (2025-06-15) https://sonofastag.com/blogs/stories/culture-clash-hash-print-and-operation-liberation-the-muddled-history-of-the-hawaiian-aloha-shirt
(閲覧日:2025-12-12)